もう少し「回顧的倒錯」の話をしよう。
遡るならばニーチェということになるのだろうけれど、フーコーの受容とともに我々は「系譜学」という方法になじんだ。永井均の言い回しを借りればそれは「現在の自己を成り立たせていると現在信じられてはいないが、実はそうである過去」「思い出として現存することを拒否された過去」についての言説であり、とりあえずは「現在の自己を成り立たせていると現在信じられている過去」「「思い出」という形をとって現存しているもの」についての言説としての解釈学と対比される。王寺が読むモンテスキュー、ルソーが批判する社会契約説は、まさにこの解釈学としてはたらきながら、現在を過去に投影してありもしない偽の起源をでっちあげる――そのようにして現在を正統化しようとする――「回顧的倒錯」である。
ただ王寺によればそこでモンテスキュー、ルソーはそうした起源の捏造によるその結果としての現在の正統化、を批判するために、系譜学的に「現在の自己を成り立たせていると現在信じられている過去」を発掘して現在を異化するわけではない。社会契約論がやろうとしたことは、ただ単に因果的な歴史物語を提示するだけではなく、それは社会秩序を樹立しようという意志に導かれたものである、という目的論的図式をそこに重ね合わせるものであった。モンテスキューもルソーもともにこの因果的説明と目的論的正統化の癒着を拒絶し、両者を切り離す。その上でまずは、人間の意志や希望など裏切る形で展開する、歴史の因果的展開のどうしようもなさを冷徹に認識するところから始める。そしてモンテスキューの立法論は、いかなる法も政策も、この客観的な因果メカニズムを無視してはむなしいだけのものであり、むしろその重さを足場として社会秩序は形成されるのだ、とする。それに対してルソーは、この因果秩序の更に根底に潜む人間的自然に反しないような社会契約であれば支持するに値する、とし、その実現可能性について壮大な思弁を展開する。
どういうことかといえば、目的論的正統化の図式を温存させたままでは、それと因果的説明をきちんと区別しないままでは、系譜学は別の起源の提示によって別の目的論的正統化の言説を語るだけに終わってしまう、ということだ。(実は現代の「分析的ニーチェ研究」におけるニーチェも、このような因果性の水準でものを考える自然主義者として描かれるという。)
そうすると、因果連関と、個人によるものであれ集団の社会契約によるものであれ、自由意志に基づく意図的、目的的行為とは全く別の水準に属するものとして分離されてしまう。モンテスキューの立法論も、ルソーのそれも、そのような水準で捉えられている。だからモンテスキューのそれは乱暴に言えば「保守主義」的なものにとどまるのであり、他方でルソーの立法者は、到達点の『社会契約論』においては、アテナイのソロンのように、あるいはのちの人類学が収集する神話伝承の中に頻々と登場する「外来王」のように、神のごとき英知を持って優れた法を人民に与えながら、その法を人民に強制する権限を持たない。『社会契約論』の世界では適切な手続を通じて人民が到達した合意は定義上正しいものでしかありえない。しかしそのような合意の結果として立てられた法が、冷徹な自然の因果連関によって許容されるものかどうかなどわからない。そのような合理的な法は神のごとき英知を持った誰かが外側から押し付けるしかないが、それが本当に押し付けられたら――強制されたら、それは正しいものとはなりえない。
スコットランド啓蒙とフランス重農主義からスミスを介して19世紀経済学へと流れ込んだのは、モンテスキューのそれにむしろ近い、幸運にも人間にとって受容可能な因果連関が世界を支配しており、立法はそこをファインチューニングすればよい、というヴィジョンであったのに対して、ルソーから社会主義者たちを介してマルクスへと流れ込んだのは、その暴力的な因果連関の逃れがたさを理解した上で、それでも世界を不平等へと引き裂くその力にいかにあらがうか、という課題であった、とまずは言えよう。ただそこで不幸があったとすれば、その課題はマルクスにおいて――少なくともその継承者たちにおいて、少なくともルソーまではそうであったように政治の課題としてではなく、階級闘争という戦争によって達成されるべき課題とされてしまった、あるいは、まさに因果連関そのものとして(歴史の鉄の法則性として)達成されるべきものとされてしまったことである。




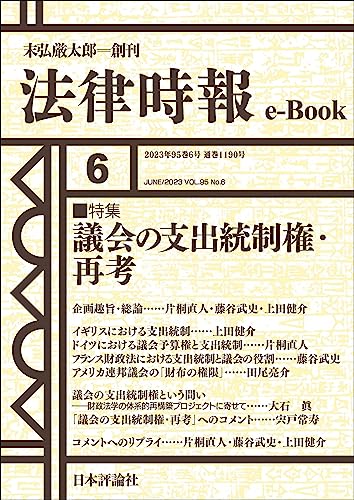


![ディープラーニングを支える技術 ——「正解」を導くメカニズム[技術基礎] Tech × Books plus ディープラーニングを支える技術 ——「正解」を導くメカニズム[技術基礎] Tech × Books plus](https://m.media-amazon.com/images/I/51rVlNIz96L._SL500_.jpg)















