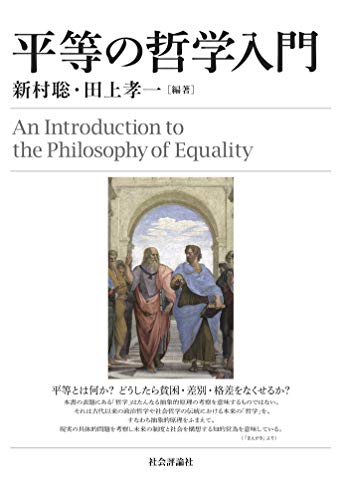理工系学生のための現代倫理学入門のこころみ
(2021年2月12日 高知工科大学講義「日本人の教養」用原稿)
1.長めの導入 文系科目――人文科学とは?
高校科目の「倫理」は大体道徳を中心とした日本思想史、東洋思想史、西洋思想史をざっと眺めたうえで、現代哲学を道徳哲学=倫理学中心に瞥見し、それにプラスして青年心理学をちょこっと、という変な構成になっている。こんな風になったのにはそれなりに理由があるのだが、それには触れない。
高校時代の地歴公民――昔の社会科というのは変な構成になっている。高校数学は大学以降の数学の準備であり、高校理科の物理・化学・生物もおおむね大学以降の物理学・化学・生物学の準備段階である。しかし高校地歴公民は?
地歴から行こう。世界史・日本史は一応大学以降の歴史学の準備になっていなくもない。しかし地理は大学の学問としての地理学への準備というわけではない。高校地理の半分(地理B)は世界各国、各地域の諸事情についての雑学という色彩が強く、その意味では経済学・政治学・国際関係論などにおける地域研究の準備といった方がまだしもである。そう考えると日本史・世界史にも歴史学プロパーというより社会科学の準備という性格が強い。
では公民の方はどうか? 現代社会、倫理、政治経済というのはいったい何か? 現代社会は社会学の、倫理は倫理学を含めた哲学の、政治経済は政治学・法律学・経済学の準備となっているのか?
高校社会(地歴公民)は理科と違って暗記科目だ、とよく言われるし、実際その批判は当たっていなくもない。どういうことかといえば、高校の物理と化学は知識を詰め込むだけではなく、基礎的な理論を教わり、その使い方を練習するという意味で、大学以降の学問の準備となっているのだが、高校の地歴公民にはそのような色彩が薄い。高校の政治経済で生徒たちは、経済学の基本的な考え方や理論を教わるわけではないし、法解釈の仕方を教わるわけではない。哲学者の名前と彼らが提示したアイディアのことは教わるが、その使い方を教わるわけではない。よくできる生徒たち、難関大学の受験に挑む受験生たちには、日本史や世界史において、ただ歴史的事実の知識を詰め込まれるのではなく、それらの有機的連関の重要性を教わるのだが、その有機的連関の解明こそが経済学、政治学、社会学といった社会科学の主題である、ということまでは(はっきりとは)習わない。
大雑把に言えば、高校理科では物理を中心に少しは理論が体系的に教えられるけど、高校社会(地歴公民)でははっきりと主題的には教えられない。だから「社会科は暗記科目」と言われるのである。でも、なぜそうなっているのか?
ひとつには社会科学においては、自然科学、特に物理学におけるほど、はっきりと確立しており、なおかつ体系的に整理されて、学ぶことが簡単な「理論」というものがないことが非常に重要なポイントである。社会現象のほとんどはいわゆる複雑系であり、扱いづらい。もうひとつ重要なことは、理論を検証する実証の困難さである。自然科学の大きな発展の理由のひとつは、実証の手法としての実験の隆盛であるが、社会科学においては実験は不可能ではないにせよ著しく困難であり、実験による研究対象への積極的介入ではなく、受動的な観察を主たる実証手法とせざるを得ない(社会――人間を対象とする実験には、固有の倫理問題も付きまとう)。さらに重要なのは実証研究のデータ処理における統計という方法の困難性である。社会科学のような複雑な対象の理解において有益な知見を得るために、特に理論が追い付かない場合には大量観察とそのデータの統計的処理、という方法が非常に有益であり、実際今日の科学研究において統計的手法の必須性はもはや常識となった感があるが、実のところ今日的な意味での統計的手法の確立は意外なほど最近である。極端なことを言えば、高校で習うレベルの物理学の発展には、統計学の助けを得る必要は基本的にはなかった。理論的探究においてはもちろんのこと、実証においても、データの統計処理を必要とするような局面は、20世紀にはいるまではさほどなかった。ガウスによる誤差の理論的な取り扱い、正規分布と最小二乗法の発見は既に18世紀末になされていたというが、それが科学研究において本質的に重要なものとしての地位を得るのは20世紀以降、フィッシャーらによる、主として農業や製造業の実践的な現場における実験計画法の確立以降ではないだろうか。
そもそも、こうした大量データの統計処理という作業は、データの収集と整理はもちろん、それらのデータの計算処理、解析の両面において、あまりにも大きな労力を必要とするものだった。これは今日のインターネット社会、人間のありとあらゆる行動がデータにとられて蓄積される方向に進みつつあるのみならず、そうしたデータの解析が飛躍的に容易になった現代のわれわれには、少々想像することが難しいかもしれない。しかしながら還暦まであと2年となった私は覚えている。1980年代、高校時代にようやく、街のゲームセンターのゲームがほぼ全部「テレビゲーム」となり、お金持ちかつ好事家の友人のうちにごく初期のパソコンがはいるようになったが、そこで大学に入学しても、依然として情報処理の授業は、計算機センターの大型機に食わせるためのパンチカードに穴をあけるところから始まっていたのを横目で見ていた。大学院に入ってからはパソコンにも表計算ソフトが標準装備され、簡単な回帰分析程度ならできるようになったが、数十組程度のデータをえっちらおっちら手打ちするのがせいぜいだった。
乱暴に言えば社会科学においては長らく、いやひょっとしたら依然として、少数の確立された法則から演繹的に組み立てたモデルや、厳密な計測によって得られた知見に頼るよりも、大雑把な「中範囲の理論」と直観的な記述の方が有効な局面が多いのかもしれない。無機的な物理世界とは異なり、生態系や人間社会といった高度に複雑なシステムにおいては、演繹的なモデルも複雑になりすぎて理解も操作もしづらくなることが多いし、また管理された実験室とは異なって未知のノイズを統制することも難しい。だから厳密な方法で積み上げるための労力が膨大となり、少なくとも短期的には場当たり的な人間の直観や経験知の方が有用になることも多い。もちろん近年では、人間のこの直観や経験知に対して、機械学習が有力なオルタナティヴとして迫撃中であるわけだが、ブラックボックス性は解消されるどころか人間の場合以上になりかねない。
このような事情が、高校までの文系科目、具体的には地歴公民、社会科が高校までは暗記科目となっている理由――人文社会科学における理論の教育が、大学以降にずれ込む理由の大きな部分を占めている、と言えよう。ただこれだけであれば、理系科目においても、生物、地学が暗記科目となってしまっている理由もまた基本的には同様であると言えよう。人文社会科学においてはこれに加えて「意味理解」という課題が加わる。ではこの「意味理解」とは、あるいは「意味」とは何か? 以下では、この「意味」という現象に、非常に偏った、しかし偏った分単純でわかりやすいアプローチを仕掛けてみる。
解析力学を習うと「最小作用の原理」で物理世界を統一的に理解しよう、というアプローチに出会うだろうが、生物学の世界でも、代謝や行動を理解する際にこのアプローチは有用である。そして何より進化、自然選択というアイディアは、このような「最小作用」の経路が実現する――最適な代謝や行動を行う生き物が出現して繁栄するメカニズムを描き出す。
そしてこのロジックは人間行動の理解においても、とりあえず経済学において利益の最大化、コストの最小化として経済行動を理解、説明するという形で威力を発揮し、更に心理学において経済行動以外にも一般化された。ただし現実の人間は複雑であり、最大化しようとする目標は必ずしも自己の経済的利益だけではない。
そもそも人間を含めた多くの――具体的に言えば複雑な脳神経系を備えた動物の行動は、快楽を求め、苦痛を避けるという方向で理解することがある程度できるが、快楽の追求=苦痛の回避と、効率的な繁殖は必ずしもイコールではない。大雑把な傾向として、動物個体が快楽を求め、苦痛を避けることによって生き延びて繁殖するチャンスを高めるというだけのことである。「快楽」の定義上、心ある動物は快楽を求めている(心あるものが求め、それを得ることによって満たされる対象とは、まさに定義上それ自体が快楽、ないしそれを与えてくれるものであろう)とは言えても、繁殖を(心あるものにのみ可能な仕方で、つまり自覚的に)目指しているとは言えない。そして更に、繰り返すが、人間の(そしておそらくは人間以外でも、とりわけ高度な認知能力を持つ動物の)追求する快楽は複雑で多種多様であり、「快楽を追求している」という枠組みのみではその行動を十分に理解し、説明することはできない。つまり人間行動の理解と説明においては、様々な生の局面で、具体的にどのような快楽を、どのような目標を追求しているのか、をまず理解した上でないと、「快楽・利益の最大化」といった説明原理の使いどころがないのだ。
伝統的に人文科学で「意味理解」と呼ばれてきたものを、理系――自然科学の枠組みに引きつけて解釈するならば、このように考えることもできるだろう。多くの場合、人間行動の理解においては、単純な経済学流に「どうやって自己利益を最大化しようとしているのか?」という問から出発するよりも、まずは「何を自分にとって大事な利益とみなしているのか?」という問を立てることの方が重要である場合が多いのである。
2.哲学とは?
さて人文社会科学とは何かという話を、理系――自然科学を標準として考える人たちに理解しやすいようにという頭で話してきたわけだが、「人文科学」といわず「人文学」という言い方をすることもあり、果たして「人文科学は科学か?」という疑問を抱く人もいるだろう。
人文社会科学の対象が典型的な複雑系、つまり普遍的な基本法則からの演繹だけではその有意義な理解が成り立たない、ということは、言い換えるとそこでは普遍性、一般性だけではなく物事の個性、唯一無二性、一回性の方に注意が払われる、ということでもある。ここでも再び高校で暗記科目扱いをされてきた生物・地学との共通性が浮かび上がる。生物現象の理解においても、生物進化のプロセスは非可逆的で一回性の高い、唯一無二の歴史過程であることが強く意識されるし、地球科学や天文学でも、普遍的な物理法則による現象の理解・説明は必須とは言え、特定の地形や天体など、現象の唯一無二の個性への関心は相対的に強い。普遍的な法則が似たようなものをたくさん反復的に生み出すという側面だけではなく、その似たようなものの間にある多様性にも配慮は払われる。
こうしてみると、科学の本質、本旨が「普遍的な法則性による世界の統一的な理解」であるというひと昔前の科学観はやや的を外したものであることがわかる。統計的な方法を実証研究における必須のものとする生物科学や人文社会科学では、普遍的な法則性よりも、ものごとの個別具体的な因果連関に焦点を当てるのが科学的な実証研究である、という考え方が有力となってきつつある。そのように考えれば、必ずしも普遍的な法則による理解・説明は重視しなくとも、事実の具体的な因果連関に注目する人文的な歴史科学は、立派な科学であることになる。
ただしここで問題となるのが哲学である。もちろん哲学という言葉・概念は歴史的に、状況に応じて違った意味をもって展開されてきた、ただ今日の我々の常識的な哲学理解では、哲学と科学は区別される。また宗教、信仰とも哲学は区別される。
ヨーロッパ史を見てみれば、どちらかというと、長らく哲学と科学の区別というものはなく、まず宗教改革以降、信仰と哲学の区別が明確となる。中世においては信仰の理性的正当化を任務とするという形で、哲学は神学の下位部門のような扱いを受けていたのだが、宗教改革以降、哲学と宗教は分離独立していく。乱暴に言えば宗教的な信仰とは、ものごとを(具体的には神による世界の創造と支配、そして人間に対する救済を)理由なしにただ信じることの上に成り立つのに対して、哲学はひたすらにものごとが現にそのようになっている理由を問い続けることによって成り立つ。
そして更に、ここで有名人を持ち出すならばいまでも哲学者の代名詞っぽい扱いを受けているカント以降には、哲学と科学の区別というものも定着してくる。大雑把に言えば科学はものごとは経験的な探究であるのに対して、哲学は超越論的=先験的(経験に先立つ)な探究である、という区別だ。カント的な考え方によれば、どのような経験的探究――ものごとを実際に見聞きし、場合によっては触り、いじくり回すことによってその成り立ちや振る舞いを理解するという営みにおいても、それを可能とする前提というものがある。そしてこの、ある経験的な知識の獲得を可能とし、根拠付けている前提をどんどんさかのぼっていけば、絶対に経験的には確証できないようなレベルに達してしまう。ややこしい言い方をしたが、具体的で卑近な例を上げれば、我々は「動物とはなにか」ということについての明確な定義など知らずに、動物についての知識を経験的にどんどん獲得していくことができる。しかしながらここで「我々はどうやって動物と動物ではないものとを区別しているのだろうか?」とか生真面目に問いはじめると困ったことになるかもしれない。動物について具体的に知るためには、まずその前提として、何が動物で何が動物ではないか、を我々は知っているはずだ。でなければ調べるべき対象としての「動物」を選ぶことができないではないか? だがここでよく考えてみると、我々は動物を特徴づける――動物と動物ではないものを区別する具体的な特徴、条件についていろいろと列挙することはできても、その中でいわば動物の「本質」、必要十分条件が何であるかについては、実は明確な自覚を持ってはいないことに気づく。
カント的な考え方では、人間の知識というものは、実はこのような階層的構造を持つ。経験的な知識が成り立つことを可能とするが、それ自体は決して経験的には確かめられないような、いわば経験に先立つ=先験的(超越論的)な知識というものがある。「動物」とか「人間」とかいった概念や、あるいは論理といったものは、そういう種類の超越論的知識なのだ。哲学とはこの超越論的なレベルを対象とする学問であり、その意味で経験的な知識の探究である科学とは次元を異にする――だいたいこういうのが、カント以降人口に膾炙した、一時期常識的だった哲学観である。
そして倫理学――道徳についての学問が科学というよりは哲学の仲間、一部門であるという考え方も、ここに由来する。倫理、道徳というものは超越論的だ――この世界で現実に人は殺されているが、そのような事実があるからといって、「人を殺すことは悪いことだ」という道徳的な規範は揺るがない――、というわけだ。
実際には現代、21世紀においては、このような哲学と科学の峻別はだんだん下火になってきており、科学と哲学を断絶したものというよりは連続したものと捉える考え方が有力になってきている――そもそもこのような区別をしてしまうと、数学の立場がわかりにくくなる――が、峻別が否定されているだけで区別――それが仮に程度の差でしかないとしても――が否定されているわけではない。力点、焦点の置きどころの違いというものはある。
3.理工系学生のための現代倫理学の見取り図
知識における経験的な水準と先験的=超越論的な水準の区別というのは、哲学風に言えば認識論の問題であるが、倫理学の主題である道徳を含めた、「である」の水準と「べき」の水準、事実と規範・価値の水準の違いというのは、どのような性質のものだろうか? 先の言い方だと後者の区別は前者の区別の応用編で、事実は経験的な水準にあり、規範・価値は超越論的な水準にある、という風な話に聞こえるかもしれない。実際このような考え方は20世紀前半に大きな影響力を持った。経験的な水準と超越論的な水準をきちんと区別したうえで関連付け、現代的な科学の基礎固めをしよう――正しい科学的研究のための基準を作ろう、という一種の思想運動として、20世紀前半の科学哲学における有力なプログラムとしての論理実証主義、というものがあったのだが、この立場から倫理学を展開しようとした論者の間で有力だった考え方は、道徳的な判断というのはいくつかの基本的、根本的な道徳原理とされるものからの、適切な論理的推論によって導かれるものだが、そこでのあらゆる道徳的推論の基礎となるはずの根本的な原理には、それ以上さかのぼって理由付けすべき更なる基礎というものは存在しない、というものだった。そして宗教・信仰の場合のように、そうした根本原理は神によって与えられた啓示であり、それゆえに正しい、という理屈をとらないのであれば、道徳的判断には根拠がない、ということになる。すなわち道徳的判断とは、突き詰めればその判断主体の無根拠な選択、あえて言えば独断的な好み、気分に還元されてしまう、というのである。
このような考え方――道徳的判断とは客観的な事実についての判断ではなく、主観的な態度の表明に過ぎないという立場は、のちに情動主義、表出主義などと呼ばれるが、20世紀前半の特に英語圏の倫理学において有力なものとなった。この立場をとると道徳的判断が客観的、つまりは普遍的で公共的でもあるように見えるのは単なる錯覚であり、実際にはそれは独断的、主観的な好みの表明でしかない、ということになりかねない。そこで「道徳判断は客観的ではないが、だからと言って単なる私的な好みの表明ではなく、普遍的で公共的である。しかしその普遍妥当性の理由は科学的知識におけるような客観的事実性ではない、ではそれはそのようなものか?」といった問いかけがさらに生まれる。さかのぼればカントの道徳哲学も実はそのような問題設定を行っていたことも確認される。
道徳的判断が客観的事実判断ではないが、さりとて単なる独断でもない、となれば次に出てくる有力な考え方は規約主義、つまり道徳とはある種の共同主観性、集団的な約束、決まり事である、というアプローチだ。ただしこのような規約主義をとっても問題は発生する。人々がそれに合意さえすればなんでもあり、というわけではなく、たくさんの人々に受容されて規約になりやすい判断と、そうではないものとがあり、その差は何か? といった風に。その困難を突き詰めていった果てに「規約になりうるものとなりえないものとの違いが客観的な事実としてあるならば、実はそれは道徳的事実としか呼べないものであり、となれば道徳的判断も事実判断の一種だと言って差し支えないのではないか?」といった議論も20世紀末以降有力となる。しかしこの場合には「Aをすることが道徳的に正しいということは客観的事実である。しかしながら私はAしたくない」という誰かの判断は、道徳的に正しくないかもしれないが、決して非合理的ではない、というパズルが生じてしまう。振り返ってみると、表出主義的な発想においてはこのパズルが生じえず、それがこの立場の強みであったわけだ。
――20世紀以降の哲学的倫理学においては、大まかに言ってこのような議論の流れがあった。それは「道徳(的判断)とはいったい何か?」という問いをめぐるものであって、伝統的に倫理学の問いの中心であったはずの「何が道徳的に正しいのか?」という問いかけではないことに注意されたい。このような流れを「メタ倫理学」といい、それに対して「何が道徳的に正しいのか?」を具体的に問う営みを「規範倫理学」と呼ぶようになった。
現代的な規範倫理学の原点は、またしてもカントとその時代にさかのぼり、カントの倫理学と、ジェレミー・ベンサム以来の功利主義の倫理学との綱引きとして、以降の規範倫理学――人はどのようにふるまい、どのように生きるべきか、そのために社会の枠組みはどのようなものでなければならないか、をめぐる問いかけ――の歴史は描かれることが多い。しかしながら20世紀後半から、実はこのような倫理学の展開は近代的な偏向であり、本来の――西洋の、いやことによったら人類史そのものの――オーソドックスな倫理学、道徳哲学からの逸脱ではないのか? という問いかけが行われるようになった。ここでおーそどくしーとして参照されるのはアリストテレスであり、中世のカトリック神学、とりわけトマス・アクィナスであるが、中国思想などにもそのカウンターパートが見いだされることも多い。
カント主義と功利主義の対立とは、後者が善を個人(更に感覚的生物全般)の快楽、幸福の実現と同一視して、正義を公的なレベルでの善の促進(ベンサムの言う「最大多数の最大幸福」)とみなすのに対して、前者が正義の根本を一人ひとりの個人の尊厳を守ることにおく、というものであり、たしかに対極的な正義、更には道徳理解に立っているが、どちらもそこで具体的な個人への生き方の指針、社会的制度構想を提示するときには、個人の内面には立ち入ることなく、その行為、行動の仕方に指示を出すにとどめる。具体的に言えば「よい行い」「正しいふるまい」を指示するにとどめて「人としての正しいあり方」には極力立ち入ろうとしない。道徳的評価の対象は、あくまでも行為、個別の行為やその仕方であって、行為の主体である人間の性質、人となり存在のありようそのものではない。
しかしながら現代においても、我々の道徳的な言葉遣いにおいて「よい行い」「悪事」という表現だけではなく、「善人」「立派な人」「悪人」「下衆」といった表現もごく普通のものであり、行為だけではなく、個人の性質、人となりもまた我々は普通に道徳的評価の対象としている。アリストテレス、トマスが体現するようなオーソドックスな倫理学の基本的な考え方とは、このように「人となり」をこそ道徳的評価の基本的な対象となし、正しい行為の指針の提供より、こうした「人となり」の涵養をこそ倫理学の主題とする。ここでいう「人となり」は伝統的には徳、ギリシア語でarete、ラテン語でvirtusと呼ばれているのであるが、このような徳倫理学こそが西洋の倫理学の正統であり、カント的な流れにせよ功利主義にせよ、そうした正統からの逸脱である――という考え方が、20世紀末以降有力となってきている。
このような徳倫理学が、近代においていったん衰退したことには理由がある――「人となり」「人格」を丸ごと格付けし評価することを認める、というよりそれをこそ道徳的判断の中心とする徳倫理学は、差別を容認し正当化する論理へと転じかねないからだ。それに対して個人の人格の尊厳を絶対化するカントの発想は、人間同士の平等を、ある尺度で測ってそれでもって「等しい」とすることによってではなく、一人ひとりのかけがえのなさゆえに、あらゆる比較を拒絶することによって逆説的に「比べようもないから等しいと扱うしかない」という形で基礎づけようとするものである。それは古典的な徳倫理学の考え方とは鋭く対立する。
このような対立は、規範倫理学のより具体的な現場での実践的適用を目指す応用倫理学においても無縁ではない。具体的には、生命医療倫理学をはじめとする先端科学技術の倫理学においては、伝統的な専門職集団の職能倫理(医療の場合の「ヒポクラテスの誓い」に象徴されるような、専門家の職能への誇りに支えられた集団的自己規制)の限界が強く意識された。先端科学技術の展開をもっぱら専門家に任せ、その社会的コントロールもその自己規制にゆだねることは、非専門家の方が圧倒的多数を占める社会にとって危険であるのみならずアンフェアであり、医療における「インフォームド・コンセント」のように、専門家と非専門家との間の、同じ市民社会の成員、同胞としての対等性を確保する仕組みを作らなければならない、というのが現代的な応用倫理学の立場であり、カント主義や功利主義の議論はそれを基礎づけようとした。
しかしながら先端技術の現場においては、いかなる努力をもっても対等化できない圧倒的な非対称性がしばしば顔を出す――というより、人間社会の根底にはそのような非対称性が存在し、先端科学技術の応用の現場において容赦のない形で露出する。生命医療技術の現場における胎児や、地球環境問題や福祉国家財政の持続可能性の際に論じられる、いまだ生まれない将来世代のように、圧倒的に受動的であるしかない存在、自らの権利を決して自ら主張しえない存在(将来世代はそもそも「存在」だろうか?)の尊厳を、どうやって尊重すればよいというのだろうか?
このような圧倒的な非対称性の露出への問題意識が、近代的な倫理学の限界を意識させ、危険を承知の上で徳倫理学的な発想を召喚しようとすることへとつながっているのである。
*参考文献
稲葉振一郎『社会倫理学講義』有斐閣より2021年3月刊行予定
![社会倫理学講義 [ 稲葉 振一郎 ] 社会倫理学講義 [ 稲葉 振一郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1741/9784641221741.gif?_ex=128x128)
- 価格: 2090 円
- 楽天で詳細を見る

- 価格: 2090 円
- 楽天で詳細を見る